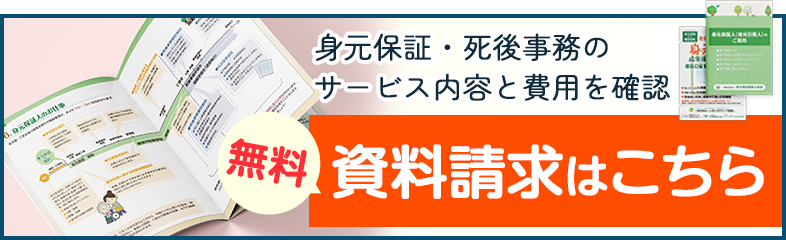ご自身のご逝去後に発生する手続きは死後事務だけではありません。葬儀供養の手配や家財処分を進めつつ、遺された財産を分配する相続手続きも進めていかなんければなりません。
いきいきライフ協会®せとうちでご相談をお引き受けする方のなかには、「遺言書を作っておけば、葬儀や供養も含めてすべて安心」とお考えの方もいらっしゃいますが、実際には、遺言書と死後事務委任契約は役割が大きく異なり、遺言書だけでは死後の事務全般をカバーすることはできません。
ここでは、その違いと手続きについて確認していきましょう。
「死後事務」と「相続」:異なる2つの手続き
死後事務と相続はともに死後に発生する手続きですが、以下のような違いがあります。
死後事務手続き
- 死亡届の提出(届出人には要件あり)
- 葬儀や供養の手配
- 納骨や永代供養への対応
- お部屋の片付けや遺品整理
- 水道・電気・ガス・電話などライフライン契約の解約
- 入院費や施設費の清算(預託金を活用)
- 保険料の過払い還付請求 など
相続手続き
- 戸籍の収集による相続人の調査
- 財産や負債の調査
- 預貯金の解約
- 不動産や自動車の名義変更
- 相続税や負債の精算
- 還付金の受領 など
このように、死後事務が「葬儀や清算など相続人でなくてもできる手続き」なのに対し、相続は「財産を承継するために相続人が行う法律的な手続き」です。行う業務が近いようで異なりますので、生前準備で行うべき対策も異なります。
遺言書では死後事務に対応できない
遺言書は、あくまでご自身が遺した財産を「誰に」「どれだけ遺すか」を指定する文書にすぎません。遺言書のなかで「遺言執行者」を指定しておけば、亡くなった後にその人が遺産分割や名義変更などの手続きを進めてくれますが、葬儀や供養の手配をしたり、ライフラインの解約をしたりといった財産の分配に関係のない死後事務業務までは対応してくれません。
葬儀の手配やお部屋の片付け、水道や電話の解約といった死後事務を第三者に依頼するには、「死後事務委任契約」を通じて、「死後事務受任者」をあらかじめ決めておく必要があります。
死後事務受任者と遺言執行者の連携が大切
死後事務と相続は異なる手続きではありますが、実際に行うにあたっては以下のように、死後事務受任者と遺言執行者が密接に連携して対応する必要があります。
- 入院費や施設費の精算は、死後事務受任者があらかじめ預かっていた預託金から払うこともできますが、遺言執行者が相続財産から支払うこともできます。
- 死後事務が完了して残った預託金は、相続財産として遺言執行者へ引き渡す必要があります。
- 還付金の申請は死後事務受任者ができますが、還付金自体は相続財産にあたるため、遺言執行者の管理口座(遺言執行口座)で受領する必要があります。
このように、両者が連携して動くことではじめてスムーズな手続きが可能になります。逆に連携が取れていないと、手続きが停滞したり、関係者間でトラブルが起きるリスクがあります。
いきいきライフ協会®せとうちなら死後事務手続きも遺言執行も丸ごとサポート
いきいきライフ協会®せとうちでは、身元保証や死後事務でのサポートを行うにあたり、死後事務委任契約と遺言書の両方をセットでご準備いただける体制を整えています。
身寄りがない方やご家族に頼れない事情をお持ちのおひとり様でも、両方の仕組みを整えることで安心して最期を迎えることができます。
お客様の「死後も希望通りに手続きを進めたい」という想いを実現するために、まずはいきいきライフ協会®せとうちの初回完全無料相談をご利用ください。専門家である身元保証相談士が丁寧に寄り添い、お客様に最適な準備をご案内いたします。